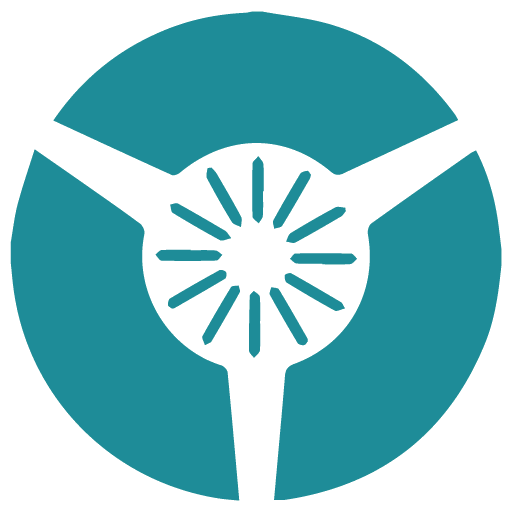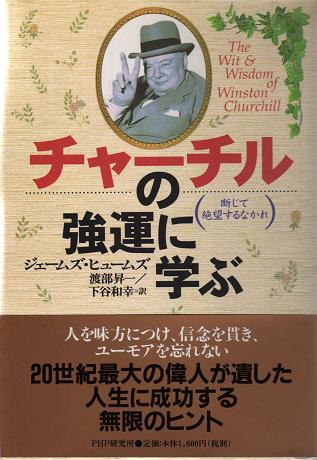
東電福島原発からプルトニウム検出、というニュース以降、
ツイッター等で、“絶望” の文字が目立つようになった。
ツイッター等で、“絶望” の文字が目立つようになった。
ex.
“絶望してはいけない、のではない。絶望すべきなのだ。
それでもそのあとにくる、見たこともないものとともに歩もうではないか。 ”
それでもそのあとにくる、見たこともないものとともに歩もうではないか。 ”
“絶望はしている。でも、生きていかなければね。 ”
etc.
◇
ホンダの本田宗一郎を陰で支えた、もうひとりの創業者、
藤沢武夫氏の経営哲学に、わたしはおおいに影響受けたので、
氏の愛読書は可能な限り、読み漁った。
藤沢武夫氏の経営哲学に、わたしはおおいに影響受けたので、
氏の愛読書は可能な限り、読み漁った。
チャーチルの『第二次大戦回顧録』は、藤沢さんとって、
切羽詰ったとき、どうしたら、ゆとりのある考えができるかを、
学んだ本だという。
切羽詰ったとき、どうしたら、ゆとりのある考えができるかを、
学んだ本だという。
藤沢さんが、感銘を受けたチャーチルの言葉を紹介すると、
~
イギリスが、ドイツの空襲に手ひどくやられていたときのこと。
「空襲警報のサイレンの発令が早すぎる。(それでは)街の消灯が早くなる。防空壕で過ごす時間が長くなる。
それで国民の精神と体力を疲弊させる。だから空襲警報の発令は遅くせよ」
それで国民の精神と体力を疲弊させる。だから空襲警報の発令は遅くせよ」
~
イギリスは武器の輸送に手一杯だったが、チャーチルは国内の物資輸送のために船をまわすよう指示をした。
「のどから手の出るほど欲しい兵器には違いないが、近頃、肉の配給が少なすぎる。
軍事用の船の一部を削って、食肉を輸送してほしい。この戦争は長いのだ。
「のどから手の出るほど欲しい兵器には違いないが、近頃、肉の配給が少なすぎる。
軍事用の船の一部を削って、食肉を輸送してほしい。この戦争は長いのだ。
国民の体力を消耗させぬことが第一だ」
~
アフリカ戦線で、必勝を誓ったイギリス軍は、「砂漠の狐」とあだ名されるドイツのロンメル将軍に
敗れてしまった。
英国議会はチャーチルが首相ではダメだと、首相不信任案を提出した。
チャーチルは次のような演説を行う。
英国議会はチャーチルが首相ではダメだと、首相不信任案を提出した。
チャーチルは次のような演説を行う。
「このような最悪の事態のとき、一国の首相の不信任案が提出できる英国民と英国議会は、
自由社会なればこそだ。ドイツやソ連では考えられないことだ」
結局、不信任案は、圧倒的多数で否決された。
◇
◇
上記画像の本は、チャーチルの言葉の寄せ集め本。
P147、【絶望 DESPAIR】 を書きだしてみる。
~
絶望するのは罪である。
未来の力となる方策を逆境から引き出す術を学ばねばならない。
未来の力となる方策を逆境から引き出す術を学ばねばならない。
決してひるんではならない、音をあげてはならない、絶望してはならない。
守るべき極めて重要な約束がひとつある。
「断じて絶望するなかれ」 ということだ。
絶望という言葉は禁句である。
「断じて絶望するなかれ」 ということだ。
絶望という言葉は禁句である。
~
おまけ、P166、【希望 HOPE】
忍耐と勇気を合わせれば、余裕と希望が生まれる。
.